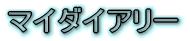
2025年10月1日(水) 晴れ
親がすぐ出てくる方がいいのか、それとも・・・
人とのかかわりの苦手な子どもが、グループ学習で本ばかり読んでいるから、ほかの子が話しかけても無駄だと自分たちで作業をしてしまってた。その子が「人とかかわりたくないから、この授業はいや」と保護者に言うと、保護者が学校に「同じグループの人から避けられていて学校に行きたくないと言ってる。どうしてくれるんだ?」担任がどんなに聞き取っても、周りにの子に聞いても、グループのほかの子も困って、声を書けづらくなってこうなっているのだろうと言います。
親がすぐ出てくる方がいいのか、それとも・・・社会に出てもその親は同じことをするでしょうか、それでいいのでしょうか。その子が周りの人達とかかわれるようなスキルをつけていかないと・・・
2025年10月7日(火) 晴れ
教室に行くことがいいことなのか?
教室の手前の教室ということで、不登校生徒の居場所づくりが始まっています。その子がなぜ教室に上がれないのかを考えることによって、いろいろなものが見えてきます。「人からいやなことをされたから教室に行きたくなくなった」は誰もが分かりやすい理由です。昔はみんなこの理由がない限り、教室に行けないはありえないと思っていたのも事実です。しかし、今はそれ以外の理由もあります。
人とのかかわりがいやな子でも教室に上がれる、一方で、人とのかかわりがいやな子は人と会うことすら嫌がる。人前にでたがる子でも突然教室に行けなくなる。などいろいろな状況がありますし、なかなか理解できないことも多いです。そう考えると、教室に行くことがいいことなのか?と思ってしまいます。
2025年10月13日(月) 晴れ
人と人のつながり
以前担任をしていた保護者が私の学校へ来られました。それも私の学校の生徒と地域の人が話し合いをする企画に参加されました。
「孫が中学生で孫世代の中学生とざっくばらんに話ができてとても楽しかった」と帰られる時に伝えて下さいました。思えば、その方の生徒は私が中学校3年間担任をさせてもらいました。いつも困った時には相談にのっていただいたり、学級で1泊2日の合宿のようなことをしたときには、いつも協力していただきました。人と人のつながりって何にもかえられないですね。本当にありがとうございました。
2025年10月19日(日) くもり
同化(無視)同情、美化(特別扱い)
古典的な差別である序列化(見下し)は理解しやすいです。しかし、平等を装った同化(無視)や、配慮したりその価値を称揚する同情や美化(特別扱い)というのが、差別につながってしまうこともある、というのはなかなか理解しにくいのではないでしょうか。これは、現実社会の中にもよくあることです。
しんどい思いをしている部落出身の相手に「そんなの関係ないよ」という言葉。相手は関係ある自分を理解してほしいと思っているでしょう。また、テレビで「障がいのある人がこんなにがんばっている」という報道。相手は障がいがあるのにという枕詞に疑問を感じるでしょう。
悪意がなく、無意識的だとは思いますが、これらが差別につながってしまうのです。
2025年10月25日(土) 晴れ
「個人モデル」「社会モデル」
障がいの「個人モデル」「社会モデル」と言われることがあります。モデルという言葉が入るので私たちには理解ができないところがあります。もともとはモデルの概念は、オーストラリア、英国、米国などの研究者や活動家によって普及・発展したものだから、日本語では理解しづらいのでしょう。
「個人モデル」とは、障害者が困難に直面するのは「その人に障害があるから」であり、克服するのはその人(と家族)の責任だとする考え方です。それに対して「社会モデル」は、「社会こそが『障害(障壁)』をつくっており、それを取り除くのは社会の責務だ」と主張します。
学校や職場、街のつくり、慣習や制度、文化、情報など、どれをとっても健常者を基準にしたものであり、そうした社会のあり方こそが障害者に不利を強いていると考えるのが「社会モデル」です。「障害があるから不便(差別される)」なのではなく、「障害とともに生きることを拒否する社会であるから不便」なのだ、と発想の転換を促す考えです。
BACK